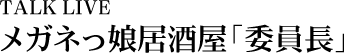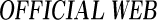大島弓子「季節風にのって」
小学館『週刊少女コミック』1973年9月号
 「ほんとうのわたし」概念が少女マンガに定着する過程を考える上で、決定的に重要な作品だ。特に眼鏡に関わって、「ほんとうのわたし」概念が二段階に展開していく物語構成は、見事と言うしかない。
「ほんとうのわたし」概念が少女マンガに定着する過程を考える上で、決定的に重要な作品だ。特に眼鏡に関わって、「ほんとうのわたし」概念が二段階に展開していく物語構成は、見事と言うしかない。
主人公は、眼鏡っ娘のアン。自分はブサイクだと思い込んで、おしゃれにはまったく関心がない。三つ編みが左右でメチャクチャでも、まったく気にしない。美しい母が身だしなみの注意をするが、眼鏡っ娘のほうは「どんなに綺麗に編んだって、あたしは変わりゃしないよ」と無頓着。しかしそれはやはり劣等感ゆえの行動だ。眼鏡っ娘は心の中で「綺麗な母様、私の悲劇が分かるまい。みんな私をおかしいと言う、みんな私を見て笑う」とつぶやく。オシャレをしたって自分が惨めになるだけだと思っているのだ。しかし、「美容師」というあだ名の男の子は、実はアンのことが好きで、自分の手でアンを美しくしてあげたいと思っていたりする。が、もちろんアンはそのことに気が付いていない。
 そんななか、超イケメン教師が学園にやってくる。女生徒たちは大騒ぎするが、なんとそのイケメン教師は、アンを初めて見るや否や、いきなりキスをしたのだ。どうやらアンのことを一目見て大好きになったらしい。いきなりキスされた眼鏡っ娘は、顔を真っ赤にして逃げてしまう。愛されているという現実をなかなか受け入れることができない。「ソバカス、ドキンガン、ひっつれたおさげ」の不細工な自分が愛されるわけがないと思い込んでいたのだ。
そんななか、超イケメン教師が学園にやってくる。女生徒たちは大騒ぎするが、なんとそのイケメン教師は、アンを初めて見るや否や、いきなりキスをしたのだ。どうやらアンのことを一目見て大好きになったらしい。いきなりキスされた眼鏡っ娘は、顔を真っ赤にして逃げてしまう。愛されているという現実をなかなか受け入れることができない。「ソバカス、ドキンガン、ひっつれたおさげ」の不細工な自分が愛されるわけがないと思い込んでいたのだ。
しかしイケメン教師は、全身でアンへの好意を示し続ける。激しく好意を示され続けたアンは、どうして自分のようなブサイクが好かれるのか、疑問に思う。「いったいあの人、わたしのどこに魅力を感じたのだろう?」 その問いに対する母親の答えが、「ほんとうのわたし」概念を掴む上で極めて重要だ。「あなたがあなたであれば、誰だって魅力的なのよ」。
これは、「好き」と「愛」の違いを端的に示した言葉だ。「好き」と「愛」の決定的な違いは、「代わりがある」か「代わりがない」かという点にある。
 たとえば、「愛しているタイプ」という言葉が日本語として不自然な一方で、「好きなタイプ」という言葉には違和感がないことを考えると、分かりやすい。「好きなタイプはショートカットだ」と言えば、ショートカットならA子だろうがB子だろうがZ子だろうが、誰だって「好き」ということになる。「好き」という言葉は、A子でもB子でもZ子でも誰でもいいという、「代わりがある」という状況で使う言葉なわけだ。逆に「愛しているタイプ」という日本語がありえないのは、「愛」とは「代わりがない」ものに使う言葉だからだ。A子を愛していると言ったとき、A子がショートカットだろうがロングヘアだろうが愛しているし、巨乳だろうが微乳だろうが関係なく愛している。「A子には他に代わりがいない」という存在のありかたそのものが「愛」の対象なのであって、なんらかの条件に適合するから「愛」が生まれるわけではない。我々は、交換不可能なかけがえのない存在に対して「愛」という言葉を使うから、「愛しているタイプ」という言葉には違和感が生じるのだ。
たとえば、「愛しているタイプ」という言葉が日本語として不自然な一方で、「好きなタイプ」という言葉には違和感がないことを考えると、分かりやすい。「好きなタイプはショートカットだ」と言えば、ショートカットならA子だろうがB子だろうがZ子だろうが、誰だって「好き」ということになる。「好き」という言葉は、A子でもB子でもZ子でも誰でもいいという、「代わりがある」という状況で使う言葉なわけだ。逆に「愛しているタイプ」という日本語がありえないのは、「愛」とは「代わりがない」ものに使う言葉だからだ。A子を愛していると言ったとき、A子がショートカットだろうがロングヘアだろうが愛しているし、巨乳だろうが微乳だろうが関係なく愛している。「A子には他に代わりがいない」という存在のありかたそのものが「愛」の対象なのであって、なんらかの条件に適合するから「愛」が生まれるわけではない。我々は、交換不可能なかけがえのない存在に対して「愛」という言葉を使うから、「愛しているタイプ」という言葉には違和感が生じるのだ。
母が言った「あなたがあなたであれば誰だって魅力的なのよ」という言葉は、交換不可能な唯一の存在であれば必ず「愛」の対象になるということを説明している。逆に言えば、流行を追いかけて誰かの真似をすることは、自らを交換可能な存在へと貶め、「愛」の対象から外れてしまう行為だ。たとえ「好きなタイプ」の範囲内に入ることは可能であっても、かけがえのない唯一の存在として「愛」の対象となることは不可能なのだ。眼鏡を外すことは、自らを「愛」の対象から外すことなのだ。本作では、アンは他の女どもと違ってオシャレに関心を持たずに眼鏡をかけ続けたことによって、イケメン教師にとって交換不可能な唯一無二の存在となっていたのだった。
ここに「ほんとうのわたし」概念が明らかになったように見えるが、本作がすごいのは、ここからさらに一歩踏み出していったところにある。実はイケメン教師がアンのことを好きだったのは、17年前に眼鏡でおさげでソバカスの女性を好きになったからだった。初恋の女性にそっくりだったために、アンのことも好きになったのだ。そう、つまり、アンは交換不可能な唯一無二の存在ではなかった。イケメン教師の初恋の女性の「代わり」として好かれたにすぎなかった。それは交換可能であるから、「愛」ではない。アンはそれが「愛」ではなかったことに気が付く。だからイケメン教師との恋を断念するのだ。
まあ、イケメン教師の17年前の初恋の相手、眼鏡でおさげでソバカスの女性とは、実は眼鏡っ娘の母親だったわけだけど。そしてイケメン教師も、そのことを最初から知っていた。アンに対する恋が「代わり」であることも自覚していた。だからそれは自発的に終わりにしなければならない。「眼鏡として代わりがある」というところから、一つの恋が終わったのだ。「愛」には「代わり」があってはいけないのである。
物語構成を整理すると、(1)誰とも違っているから好きになってもらえない→(2)誰とも違っているから愛される→(3)代わりだったから愛が終わる、ということになる。が、登場人物の中に一人、アンを交換不可能な、かけがえのない、唯一無二の存在として想っている人物がいた。つまり「愛」している人物がいた。「美容師」だ。ここから、新しい「愛」の物語が始まる。(2)で「ほんとうのわたし」概念が示されながら、それで終わらず、さらに(3)から「ほんとうのわたし」概念が深まっていくところが見事な構成だ。
最後に、実はこの物語構成は、西川魯介「屈折リーベ」の構成と相似形にある。もちろん西川魯介が大島弓子の作品をパクったのではない。また物語構成が相似形にあることは、プロットが似ていることも意味しない。作品の個別性を捨象して、物語構成を極度に抽象化したときに、初めて浮かび上がってくる相似形だ。両作品に共通しているのは、どちらも「愛」とは何かを真剣に追及した結果、「ほんとうのわたし」概念が美しく結晶化されていくという点にある。「ほんとうのわたし」概念をとことんまで突き詰めた時、着地点はきっとそんなに遠くにはならない。「屈折リーベ」については、しかるべきタイミングで改めて考えたい。
■書誌情報
単行本『F式蘭丸』に所収。ちょっとしたプレミアはついているが、昔の大島弓子作品ということを考えれば手に入りやすい部類か。
| ■広告■ |
| ■広告■ |